【専門医が解説】その動悸や過度な心配、もしかして不安障害かも?正しく知って、安心を手に入れる
「電車に乗ると、急に息が苦しくなって『死ぬかもしれない』と怖くなる…」
「人前で話すことを考えると、何日も前から眠れなくなる…」
「いつも最悪の事態ばかり考えて、常に何かに心配している…」
このような、コントロールできないほどの強い「不安」に、日常生活を脅かされていませんか?
それはあなたの性格が弱いからでも、気の持ちようの問題でもなく、不安障害(不安症)という治療可能な病気かもしれません。
不安は、危険を知らせてくれる大切な感情です。しかし、その警報が誤作動を起こし、危険がない場面でも鳴り響いてしまうのが不安障害です。
この記事では、不安障害とは何か、その代表的な種類である「パニック障害」や「社会不安障害」について、原因から治療法、そしてご家族にできるサポートまで詳しく解説します。正しい知識を身につけ、つらい不安から抜け出すための一歩を、一緒に踏み出しましょう。

不安障害とは? – 「正常な不安」と「病的な不安」の違い
試験の前や大事なプレゼンの前にドキドキしたり、心配になったりするのは、誰にでもある自然な「不安」です。この不安があるからこそ、私たちは準備をしたり、危険を避けたりすることができます。
しかし、不安障害における不安は、その程度や状況が異なります。
- 過剰な不安:客観的に見てそれほど危険ではない状況でも、非常に強い恐怖や不安を感じてしまう。
- コントロールできない不安:不安に思う必要がないと頭では分かっていても、どうしてもその考えが頭から離れない。
- 生活への支障:不安や恐怖を避けるために、学校や会社に行けなくなったり、友人と会えなくなったりと、日常生活に大きな支障が出てしまう。
このように、不安の警報システムが過敏に、そして過剰に働きすぎてしまうのが「病的な不安」、すなわち不安障害です。
不安障害の主な種類
不安障害にはいくつかの種類がありますが、ここでは代表的なものをいくつかご紹介します。
- パニック障害(パニック症)
突然、理由もなく激しい動悸や息苦しさ、めまいなどの身体症状とともに、「このまま死んでしまうのではないか」という強い恐怖に襲われる「パニック発作」を繰り返す病気です。
発作が起きていないときも、「また発作が起きたらどうしよう」という強い不安(予期不安)に悩まされたり、発作が起きた時に逃げられない場所(電車、人混み、美容院など)を避けるようになり(広場恐怖)、行動範囲が極端に狭まってしまうことがあります。 - 社会不安障害(SAD)/社交不安症
人から注目される場面や、他人に評価されるような状況に対して、過剰な不安や恐怖を感じてしまう病気です。「恥をかくのではないか」「変に思われるのではないか」という強い不安から、顔が赤くなる、汗をかく、声や手が震えるといった身体症状が現れ、そのような状況を必死に避けようとします。
(例:人前でのスピーチ、会議での発言、電話応対、初対面の人との会話など) - 全般性不安障害(GAD)
仕事、家庭、健康、経済状況など、生活における様々な事柄に対して、漠然としながらも過剰で、コントロールできない心配や不安が長期間(6ヶ月以上)続く病気です。常に緊張状態にあるため、疲れやすさ、集中力の低下、筋肉のこわばり、不眠などの身体症状を伴うことも多くあります。
不安障害の原因
不安障害がなぜ起こるのか、その原因は一つではありません。脳の機能的な問題、遺伝的な要因、その人の気質、そして環境的なストレスなどが複雑に絡み合って発症すると考えられています。
- 脳の機能:不安や恐怖を感じる「扁桃体」という部分が過剰に活動したり、不安を抑制する神経伝達物質(セロトニンなど)のバランスが乱れたりすることが関係していると考えられています。
- 遺伝的要因:家族に不安障害の方がいると、発症しやすい傾向があることが知られていますが、必ず遺伝するわけではありません。
- 性格・気質:もともと心配性、完璧主義、神経質、人からの評価を気にする、といった傾向のある人は、不安を感じやすいと言われています。
- 環境的要因:過去のトラウマ体験や、強いストレスに長期間さらされることが、発症の引き金になることがあります。
不安障害の症状 – こころとからだに現れるSOS
不安障害の症状は、精神的なものだけでなく、身体にもはっきりと現れるため、ご本人は大変な苦痛を感じます。内科や循環器科を受診しても「異常なし」と言われ、原因が分からずに悩んでいる方も少なくありません。
【こころの症状】
- 強い不安、恐怖、パニック
- 絶えず続く心配事
- 危険が迫っているような感覚
- イライラ、落ち着きのなさ
- 集中力の低下
- 現実感がない感じ
【からだの症状】
- 循環器系:動悸、胸の痛み・不快感、頻脈
- 呼吸器系:息苦しさ、息切れ、のどが詰まる感じ
- 消化器系:吐き気、腹部の不快感、下痢
- 神経系:めまい、ふらつき、手足のしびれや震え、頭痛
- その他:発汗、体のほてりや冷え、頻尿、不眠

不安障害の治療 – 不安と上手に付き合うために
不安障害は、適切な治療によって改善する病気です。「性格だから」と諦める必要はありません。治療の柱は、薬物療法と精神療法です。
【1. 薬物療法】
乱れてしまった脳の神経伝達物質のバランスを整え、不安や身体症状を和らげるために行います。
- SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)など
抗うつ薬の一種で、不安障害の治療の中心となるお薬です。脳内のセロトニンの働きを調整し、不安や恐怖感を根本から和らげていきます。効果が出るまでに2〜4週間ほどかかりますが、依存性がなく、安全性の高いお薬です。 - 抗不安薬(精神安定剤)
不安やパニック発作を一時的に抑える、即効性のあるお薬です。つらい症状をすぐに和らげる効果がありますが、根本的な治療薬ではないため、SSRIの効果が出るまでの補助や、頓服(とんぷく)として使われることが一般的です。
【2. 精神療法】
薬物療法と並行して行うことで、再発しにくい状態を目指します。特に認知行動療法が非常に有効です。
- 認知行動療法(CBT)
不安を感じやすい考え方(認知)のクセに気づき、それをより現実的でバランスの取れた考え方に変えていく練習をしたり、不安だからと避けている状況に少しずつ挑戦して慣れていく(曝露療法/エクスポージャー法)ことで、不安を乗り越える自信をつけていく治療法です。
例えば、パニック障害の治療では、「この動悸は心臓発作ではなく、不安による正常な身体反応だ」と理解し、あえて各駅停車の電車に一駅だけ乗ってみる、といったトレーニングを専門家と一緒に行います。
自分でできる対処法(セルフケア)
治療と合わせて、日常生活で以下のことを心がけると、症状の安定につながります。
- リラクゼーション法を身につける
不安が高まってきたときに、腹式呼吸(お腹を意識して、ゆっくり息を吸って吐く)や筋弛緩法(体の各部分に力を入れて、ストンと抜く)を試してみましょう。心と身体の緊張をほぐす効果があります。 - 生活リズムを整える
十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動は、自律神経を整え、心の安定につながります。 - カフェインやアルコールを控える
カフェインは不安や動悸を誘発しやすく、アルコールは一時的に不安を和らげますが、長い目で見ると症状を悪化させ、依存の問題も生じさせます。
ご家族や周りの方にできること
ご本人が感じる強い不安や恐怖は、周りの人には理解しにくいかもしれません。しかし、ご家族の正しい理解とサポートが、ご本人の回復を大きく後押しします。
- 病気を正しく理解し、本人を責めない
症状は「気のせい」でも「怠け」でもなく、病気によるものだと理解してください。「しっかりしろ」「気にしすぎるな」といった言葉は、ご本人を追い詰めてしまいます。 - パニック発作が起きたら、冷静に見守る
そばにいて「大丈夫だよ」「少しすれば治まるよ」と優しく声をかけ、背中をさするなどして安心させてあげてください。「死ぬことはない」と伝えることも有効です。過剰に心配したり、救急車を呼んだりすると、かえって本人の不安を煽ってしまうことがあります。 - 本人の話をじっくり聴く
何に不安を感じているのか、どんなことが怖いのか、否定せずに耳を傾けてあげてください。 - 小さな成功を一緒に喜ぶ
治療の中で、ご本人がこれまで避けていたことに挑戦できたときは、「すごいね」「よく頑張ったね」と、その勇気を褒めてあげてください。 - 過保護になりすぎない
心配のあまり、ご本人が避けていることを全て代行してしまうと、かえって回復を妨げてしまうことがあります。本人の挑戦を、根気強く見守る姿勢も大切です。
最後に
不安障害の苦しみは、経験した人でなければ分からないほどつらいものです。しかし、あなたは決して一人ではありません。そして、その不安は適切な治療によって、必ず軽くすることができます。
「こんなことで相談していいのかな」などとためらわずに、どうか専門家である私たちにご相談ください。あなたが不安に振り回されることなく、安心して自分らしい毎日を送れるよう、私たちが全力でサポートします。



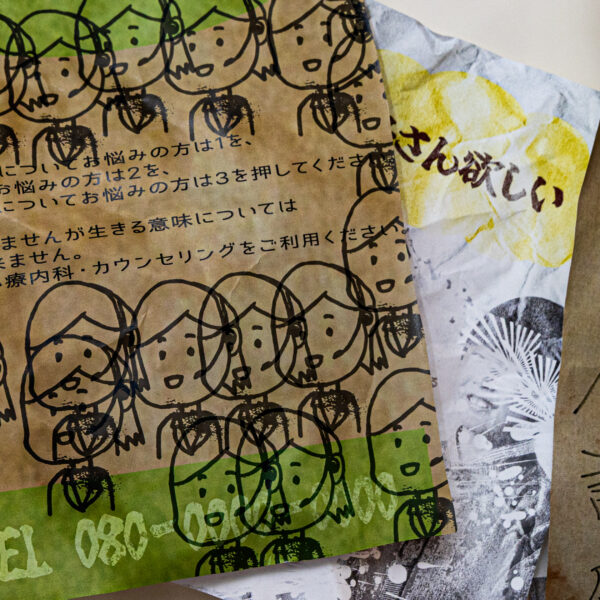



コメント